【www.guakaob.com--韩国移民】
《有关猫的成语》
关于猫的成语 第一篇
a cat nap 打个盹儿 let the cat out of the bag 放出袋中猫(泄密,说漏嘴) more than one way to skin a cat 剥猫皮各有巧妙不同(另有办法) rain cats and dogs 天上下猫,天上下狗(倾盆大雨) All cats are(或look)black(或gray)in the dark.或者We are in the same boat.也就是说:大家彼此彼此(We are all equal或We are in the same situation。就像「五十步笑百步」或「乌鸦笑猪黑」。 一言既出,驷马难追:有人译成:One word lets slip and four horses will fail to catch it. 或 A statement that once let loose cannot be caught by four galloping horses. 西方人也喜欢猫,并将猫养为宠物。但是黑猫却让西方人心生恐惧,尤其是英国人,他们将黑猫与女巫联系在上起。如果是在一个漆黑的星期五晚上碰上一只黑猫,便预示着此人会遭厄运。在英国古代的传说中,人们认为妖魔常变成黑色的动物,尤其是黑猫,还有人说黑猫就是巫婆变的。黑猫有九命,巫婆有变九次的魔法。杀死一只黑猫,她还可以再变八次。所以英语的猫还含有"心地恶毒的女人,爱说人坏话的女人"等意思。如,She is a cat(她是个包藏祸心的女人),Mrs Smith is a perfect cat(史密斯太太是个地地道道的长舌妇),The man and his wife lead a cat and dog life, and both are miserable (他们夫妻俩经常吵架,两人都感到痛苦)。It's difficult to get a man to bell the cat(敢于在危险中挺身而出的人不容易找到)。与猫有关的成语也很多,如:A cat has nine lives(猫有九命--自有天相),Cats hide their claws(猫总是藏起自己的爪子--知人知面不知心),All cats are grey in the dark (黑暗处的猫都是灰色的--人未出名时看起来都差不多),A gloved cat catches no mice(戴手套的猫抓不到老鼠--不愿吃苦的人成不了大事业),The cat shuts its eyes when stealing cream(掩耳盗铃,自欺欺人)。Care killed the cat(忧虑伤身), Let the cat out of bag(无意中泄露秘密),There's more ways than one to kill a cat(有的是办法),When the cat is away, the mice will play(猫不在,老鼠玩得自在),,like a cat on hot bricks(焦躁不安,如热锅上的蚂蚁),not a cat in hell's chance(毫无机会)。
《日语关于猫的成语》
关于猫的成语 第二篇
2. ことわざに見る猫<日本>良きにつけ悪しきにつけ、我らが猫ほど多くのことわざや慣用句に登場する動物はない。遠い昔から我々の生活に深く入り込んでいたことの現れだろう。ことわざ・慣用句に見えかくれする古人の猫に対するイメージを探ってみよう。
--------------------------------------------------------------------------------
<50音順目次>
猫足
猫面
猫が熾(おき)をいらうよう
猫が胡桃を回すよう
猫が肥えれば鰹節が痩せる
猫が茶を吹く
猫が手水(チョウズ)を使うよう
猫被り
猫毛
猫叱るより猫を囲え
猫舌
猫舌の長風呂入り
猫背
猫と庄屋に取らぬは無い
猫撫声
猫に会った鼠
猫に傘(からかさ)
猫に紙袋(カンブクロ)で後退り{关于猫的成语}
猫に九生あり
猫に小判
猫に栄螺{关于猫的成语}
猫に木天蓼
猫の魚辞退
猫の寒乞い{关于猫的成语}
猫の食い残し
猫の子はなぶると痩せ、犬ころはなぶると肥ゆる
猫の逆恨み
猫の尻尾
猫の手も借りたい
猫の鼠を窺うよう
猫の鼻
猫の鼻先に鼠を置くよう
猫の歯に蚤
猫の額
猫の額にある物を鼠が窺う
猫(の額)に鰹節
猫の前の鼠の昼寝{关于猫的成语}
猫の目
猫は三年の恩を三日で忘れる
猫は長者の生まれ変わり
猫ばば{关于猫的成语}
猫は三月を一年とす
猫跨ぎ
猫耳を洗うと雨が降る
猫も杓子も
猫を追うより鰹節を隠せ
猫を殺せば七代祟る
猫を一匹殺せば七堂伽藍を建立せるより功徳あり
鼠捕る猫は爪を隠す{关于猫的成语}
参考文献
◆「猫も杓子も」
なにもかも、だれもかれも、の意。すぐに右へならえして流行に翻弄される日本人の国民性もあってか、今でも良く使われる言い回しだ。
生まれては死ぬるなりけりおしなべて
釈迦も達磨も猫も杓子も
と一休禅師の歌にも見えるこの言い回し、鎌倉時代の末頃にはすでに使われていたようだ。それにしてもなぜ猫と杓子(水や汁ものやご飯などをすくうしゃもじ)なのだろう?語源にはさまざまな説がある。
「猫のちょっかい杓子に似たればかく言ふなるべし」とは江戸時代の学者の説
「女子(めこ)も弱子(じゃくし)も」(=「女も子供も」)の意だとするのは落語「横丁の隠居」の説
このほか、「禰宜(ねぎ)も釈氏(しゃくし)も」(=「神も仏も」)が変化したとする説、「寝子(ねこ)も赤子(せきし)も」(=「寝ている子供も赤子も」)が変化したとする説等々がある。また、杓子は家庭の主婦をさし、猫まで動員した家族総出の意味だとする説もある。
「猫も杓子も」の語源と関わりがあるかどうかは分からないが、猫が死ぬとその亡骸を三叉路の道ばたに埋め、杓子など台所のものを立てるという風習が18世紀以前からあった{关于猫的成语}
ようだ。鼠が台所を荒らすのを防いでくれたことに対する感謝の意を込めて、台所の物を立てたという。また三叉路は人通りが多いので、少しでも多くの人に拝んでもらうためだとか。
Top of This Page
◆「猫ばば」
悪事を隠して知らん顔すること、特に拾った物をひそかに自分の物にすることの意。猫には迷惑千万なこの言い回し、近世に入ってから使われるようになったらしい。 語源には2通りの説がある。
一つは「猫+糞(ばば)」とする説。猫がふんをした後、後足で土をかけて隠す習性があることから生じたというものだ。{关于猫的成语}{关于猫的成语}
もう一つは「猫+婆(ばば)」とする説。伝説によると、徳川時代の中期、江戸は本所にたいそう猫を可愛がっていた老婆がいたという。医者の祖母であったこの老婆は、30匹もの猫を飼っており、猫専用の部屋をあてがい、猫専用女中まで置いて猫の世話をさせ、大切に育てていた。ところが、この老婆にはとんでもない性癖があった。単なるもの忘れのせいか、承知の上での欲張りのせいか定かではないが、人から物をもらっても決して返礼せず、届け物を頼まれても自分の懐に入れてしまうというのだ。以来、いつからともなく「人の物を横取りする」といった場合に「猫婆」と言われるようになったという。 現在では、「猫+糞」を語源とする説が有力視されている。
Top of This Page
◆「猫被り」(猫を被る)
本性を隠して表面おとなしそうに振る舞うこと。また、知っているのに知らない素振りをすること。
語源には2通りの説がある。
一つは、猫のようにうわべだけ柔和にする意という説。猫をうわべだけ柔和で内心は貪欲だったり陰険だったりするものと捉えた表現には『猫根性』とか、『借りてきた猫』などがあるが、猫にとってはありがたくない言い回しだ。
もう一つは、ねこ(わら縄を編んだむしろ)を被る意とする説。愛猫家としてはこちらを推したいところだが…。
ちなみに英語では a wolf (fox) in lamb's skin (sheep's clothing) となり、我らが猫は無罪放免となっている。
Illustrated by Tengokuya-Uran
Top of This Page
◆「猫に小判」{关于猫的成语}
どんな貴重なものでも、どんな高価なものでも、その価値のわからない者に与えては、何の役にも立たないという喩え。確かに猫に小判を投げてやっても、匂いを嗅いで、前足で砂をかける仕草をするのがせいぜいかもしれない。一方で、小判、大判を抱えた招き猫は、実に自然に見えるから不思議だ。
同義で、「猫に石仏」「猫に経」という言い回しもある。
また、物の価値がわからないという汚名を着ているのは、猫だけではない。「犬に小判」「犬の銭見たるが如し」「犬に論語」「馬の耳に念仏」「馬に天保銭」「馬の目に銭」「牛に麝香、猫に小判」「豚に真珠」など、身近な動物が槍玉に挙がっている。
Top of This Page
◆「猫に木天蓼」
大好物の例え。また、効果てきめんであるという意味にも使う。
確かに猫は木天蓼(マタタビ)が大好きで、日頃つんとすました顔をしている猫も、木天蓼を前にすると、見ているのも恥ずかしくなるような有り様。元気のない時にも、一嗅ぎでパワーアップ。効果絶大だ。
この言い回しは、「猫に木天蓼、お女郎に小判」とつなげることもある。遊女もお金が大好きということだが、日頃本性を現さない代表が猫とお女郎で、それも好物を前にしては相好をくずすということらしい。あるいは「猫」=「お女郎」「遊女」という連想が根深くあることから、ここでも仲良く並べられたのかもしれない。
そもそも「猫」は「芸妓」の異称として使われるし、「猫は傾城(ケイセイ=遊女)の生まれ変わり」とか、逆に「傾城には猫がなる」とか、「猫」と「遊女」は一心同体のような扱われ方をしている。また、「猫の鼻と傾城の心は冷たい」という慣用句もある。 ちなみに「お女郎に小判」の代わりに、「猫に木天蓼、泣く子に乳房」とつなげることもあるようだ。
Top of This Page
◆猫(の額)に鰹節
好物をそばに置いたのでは油断がならないことの例え。過ちをおこしやすい、危険な状況であること。
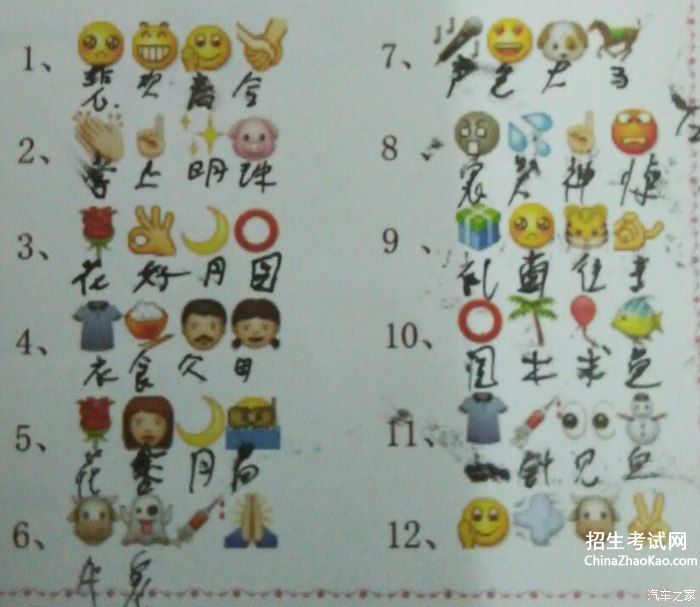
同じ好物でも、前述の「木天蓼」だと、効果てきめんの例えとなり、「鰹節」だと危険で油断できないことの例えとなるから面白い。確かに「木天蓼」は猫だからこそ喜ぶもので、しかも「取る」というようなアクションもしない。一方「鰹節」は人間にも大切なもの、取られては困るものだ。
取られては困るものは他にもあり、「猫に鰹節」と同義で「猫に鰹」、「猫(の額)に生鰯」、「猫に乾鮭」などがある。「猫に鰹節、道楽息子に金の番」という言い回しなど、そのニュアンスが良く伝わってくる。
「猫に鰹の番」「猫に魚(肴)の番」「猫に鰹節預けるよう」「猫の鼻先に鼠を置くよう」なども同義で使われる。
猫以外では、「金魚にぼうふら」「狐に小豆飯」「盗人に倉の番」という表現があるが、圧倒的に猫をからめた言い回しが多い。身近にいて、人間の食べ物を失敬していくのは、や
はり猫。「泥棒猫」と言われても仕方がないかもしれない。
Top of This Page
◆猫に栄螺(サザエ)

好物だが手の出しようがないことの例え。
確かに猫に大好きなサザエを預けても、自分では殻から出して食べることはできない。 「猫」の後に好物を続ける表現も、何を続けるのか、「木天蓼」なのか「鰹節」なのか、はたまた「栄螺」なのかで、意味が違ってくる。実に興味深い。
Top of This Page
◆猫が肥えれば鰹節が痩せる
猫が大好きな鰹節をかじってころころ太る一方で、かじられた鰹節は痩せ細っていくことから、一方が良ければ他方が悪くなる、一方に利があれば他方が損をすることの例え。
Top of This Page
◆猫を追うより鰹節を隠せ
猫に鰹節を食われてしまうからと、たえず番をして猫を追い払うより、鰹節の方を隠せばあっさり問題は解決することから、些末なことより、根本を正せという例え。「猫を追うより皿を引け」「猫を追うより魚を除けよ」も同義。
Top of This Page
◆猫叱るより猫を囲え
猫に魚を取られて猫を叱るより、取られないように用心することが大切、問題が起きる前に予防策を講じよ、という意味。
実際に猫を囲うかどうかは別として、予防策を講じることこそ、猫と共に暮らす者、常に念頭に置いておかなければ!
Illustrated by Tengokukya-uran
Top of This Page
◆猫の魚辞退(うおじたい)
《有猫的成语》
关于猫的成语 第三篇
《关于哭泣的成语》
关于猫的成语 第四篇